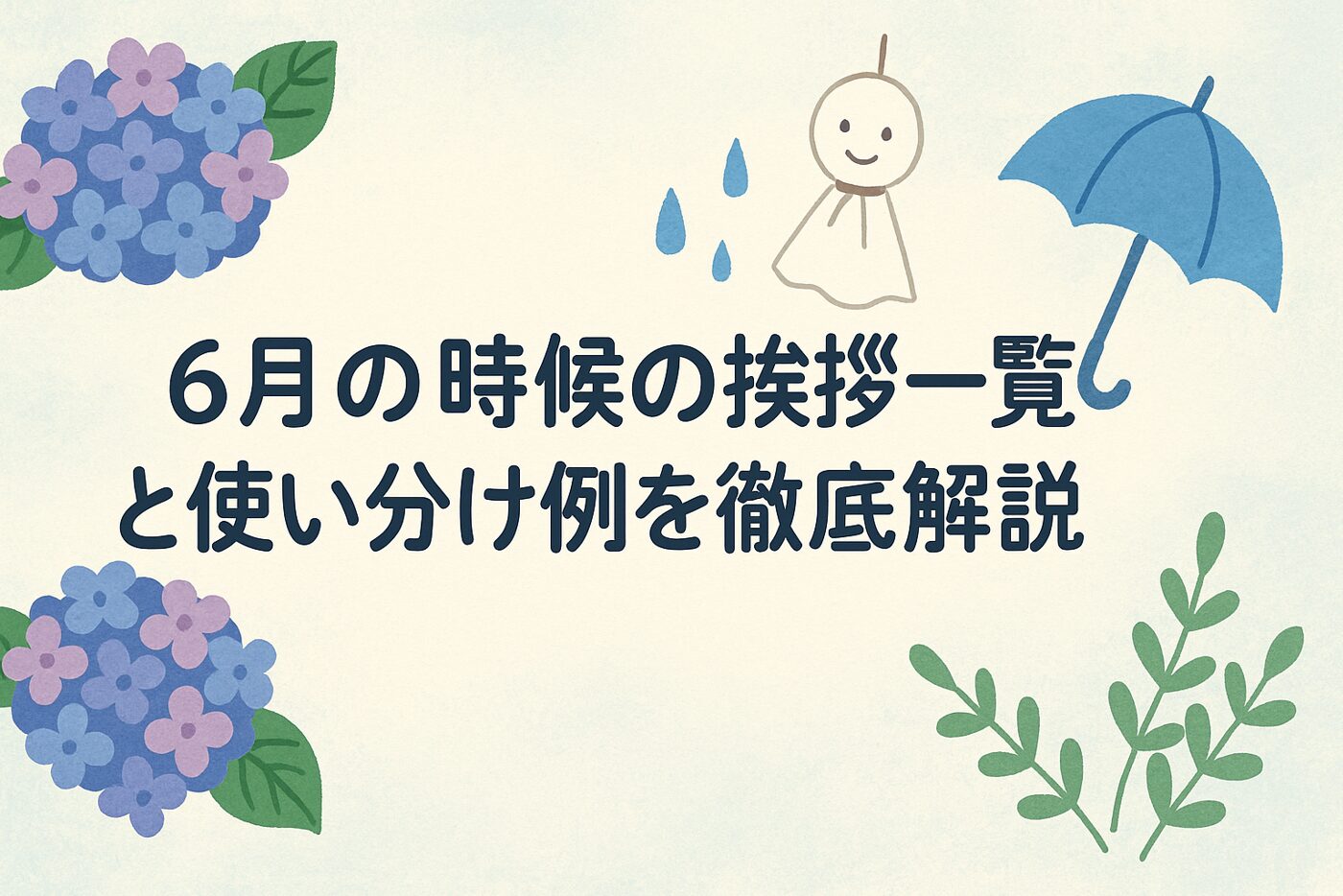6月に入り、手紙やメールを送る機会が増える中で、「6月 時候の挨拶 一覧」を探している方も多いのではないでしょうか。この記事では、5月下旬から6月上旬、中旬は何の候を使えば良いか、そして下旬にふさわしい挨拶まで、時期に応じた時候の挨拶をわかりやすくまとめています。
また、書き出しに使える自然な表現や、ビジネス文書に適した丁寧な言い回し、親しい相手へのカジュアルな挨拶の工夫、さらに学校関係の手紙やお礼状など、それぞれのシーンに応じた使い分けも紹介します。季節の移ろいを感じさせる季節の言葉を活かした挨拶文で、相手に好印象を与えられる表現を身につけましょう。
- 時期別に使える6月の時候の挨拶を把握できる
- ビジネスやカジュアルなど場面別の使い分けがわかる
- 書き出しや結びの適切な表現が学べる
- 季節の言葉を取り入れた自然な文例が参考になる
6月の時候の挨拶一覧と使い分け方
・5月下旬から6月上旬に使える挨拶
・6月上旬に使える挨拶の例
・6月中旬は何の候が適切か
・6月下旬に使える挨拶一覧
・ビジネスで使える6月の挨拶文
5月下旬から6月上旬に使える挨拶
この時期は、春の名残と夏の気配が交差する季節です。季節の移ろいを丁寧に表現することで、相手に配慮の気持ちを伝えることができます。
まず取り入れたい表現として「向暑の候」や「初夏の候」が挙げられます。「向暑の候」は暑さに向かう季節を意味し、5月下旬から6月にかけて幅広く使える便利な語句です。「初夏の候」は夏の始まりを告げる言葉として、6月上旬までが適しています。
また、「青葉若葉の候」は、芽吹いた緑が鮮やかになる様子を表す挨拶として5月下旬にぴったりです。視覚的なイメージを伴うため、読む相手にも自然の風景が思い浮かびやすくなります。
使用例
- 拝啓 向暑の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
- 拝啓 青葉若葉の候、いかがお過ごしでしょうか。
ただし、地域によってはこの時期にすでに梅雨入りしている場合もあります。そのようなときは、梅雨に関連する挨拶を使ったほうが、現実の天候に合った印象を与えられます。
このように、5月下旬から6月上旬には「初夏」や「若葉」などの語を用いて、清涼感のある季節感を演出するのが効果的です。
6月上旬に使える挨拶の例
6月上旬は、梅雨入り直前のすっきりとした気候が特徴です。時候の挨拶には、この時期ならではの自然や生活の変化に触れる表現がよく使われます。
代表的な挨拶例としては、以下のものがあります。
- 芒種の候(ぼうしゅのこう):6月5日頃から使用可能。田植えが始まる時期を表します。
- 薄暑の候(はくしょのこう):軽い暑さを感じる気候に用いられ、爽やかな印象があります。
- 衣替えの季節:身の回りの変化に触れる表現として、手紙やメールでも違和感なく使えます。
使用例
- 拝啓 芒種の候、貴社のますますのご繁栄をお祈り申し上げます。
- 拝啓 薄暑の折、皆さまにはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
- 拝啓 衣替えの季節となりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。
このような挨拶は、ビジネスでもカジュアルな手紙でも使いやすく、相手との関係性を問わず活用できます。
ただし、「芒種」や「薄暑」といった表現はややフォーマルな印象があるため、親しい相手には「初夏のさわやかな風が心地よく感じられる季節となりました」など、やわらかい語調で伝えるとより親しみやすくなります。
6月中旬は何の候が適切か
6月中旬になると、各地で梅雨入りが本格化します。この時期の挨拶では、湿気や雨に関連した言葉を取り入れることで、季節感が伝わりやすくなります。
適切な「候」の例として、以下のようなものが挙げられます。
- 入梅の候(にゅうばいのこう):6月11日前後の「入梅」から使用可能。梅雨入りを表す正式な表現です。
- 長雨の候(ながあめのこう):雨が続く時期に用いる言葉で、梅雨らしさを強調できます。
- 梅雨の候(つゆのこう):ややカジュアル寄りで、使いやすさが特徴です。
使用例
- 拝啓 入梅の候、貴社ますますのご隆盛をお喜び申し上げます。
- 拝啓 長雨の候、皆さまにおかれましてはご清祥のことと存じます。
これらの表現は、天気に敏感な時期である6月中旬にふさわしく、手紙に自然な空気感を与えてくれます。
ただし、梅雨入りの時期には地域差があるため、実際の天候とずれてしまわないように注意が必要です。北海道など梅雨の影響が少ない地域に送る場合は、梅雨に言及しない挨拶を選ぶのが無難です。
このように、6月中旬には梅雨を意識した挨拶を選ぶことで、丁寧で気配りのある文面に仕上げることができます。
6月下旬に使える挨拶一覧
6月下旬は梅雨の終盤にあたり、しとしととした長雨や蒸し暑さが特徴的な時期です。この時期にふさわしい時候の挨拶を使うことで、季節感が伝わり、相手への配慮がより丁寧に表現できます。
よく使われる表現には、次のようなものがあります。
- 長雨の候(ながあめのこう):雨が続く季節の情景を表す定番の挨拶です。
- 夏至の候(げしのこう):6月21日頃の二十四節気「夏至」にちなんだ表現で、暦を意識した丁寧な印象を与えます。
- 向夏の候(こうかのこう):夏に向かう時期という意味で、前向きな印象を添えられます。
- 小夏の候(こなつのこう):初夏の暑さが少しずつ本格化してくる様子を伝えます。
使用例
- 拝啓 長雨の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
- 拝啓 夏至の候、日ごとに暑さが増してまいりました。いかがお過ごしでしょうか。
ただし、地域によっては梅雨が明けている場合もあるため、天候と照らし合わせて選ぶ必要があります。「長雨の候」を使う場合、晴天が続いていると不自然に感じられる可能性があります。
このように、6月下旬の挨拶では「雨」「夏の兆し」といったテーマを軸に言葉を選ぶことで、季節に寄り添った印象を与えられます。
ビジネスで使える6月の挨拶文
ビジネス文書における6月の挨拶文は、丁寧で格式のある表現が求められます。文章の冒頭に時候の挨拶を入れることで、礼儀正しさと信頼感を相手に与えることができます。
この時期に適した挨拶文の要素は以下のとおりです。
- 時候の言葉(例:「向暑の候」「芒種の候」「梅雨の候」など)
- 相手の健康や発展を祝う言葉(例:「貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます」)
- 本文への自然なつなぎ(例:「さて、」や「このたびは、」)
ビジネス文例
- 拝啓 梅雨の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、○○の件につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。
- 拝啓 向暑の候、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
一方で、やや硬い印象を和らげたい場合には「梅雨の中、いかがお過ごしでしょうか」など、少し柔らかい表現を取り入れることも可能です。
注意点として、季節感と実際の気候が合っていない場合、形式的すぎる印象を与えてしまうこともあります。相手の地域や天気に配慮した表現選びが重要です。
このように、6月のビジネス挨拶では礼節を守りつつ、相手への気配りをにじませる表現を意識すると効果的です。
6月の時候の挨拶一覧と書き方のコツ
・書き出しに使える6月の時候の言葉
・カジュアルな手紙で使える表現
・学校関係の手紙に適した挨拶
・お礼状に使える6月の季節表現
・季節の言葉を活かした結び文
書き出しに使える6月の時候の言葉
手紙やメールの書き出しには、その季節を感じさせる時候の言葉を添えると、読み手にやわらかい印象を与えることができます。6月は梅雨の季節であると同時に、夏への入り口でもあるため、使える言葉の幅が広いのが特徴です。
ここでは、書き出しに適した表現を以下のカテゴリに分けてご紹介します。
フォーマル(漢語調)
- 向暑の候:暑さに向かう季節を端的に表現します。
- 芒種の候:田植えが行われる時期。6月初旬から中旬まで使用可能です。
- 梅雨の候:湿り気を含んだ季節の情緒を表します。
- 夏至の候:6月下旬に適した暦に基づく表現です。
カジュアル(和語調・口語調)
- 紫陽花が美しく咲く季節となりました。
- 梅雨空が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
- 蒸し暑さが日ごとに増してきましたね。
注意点
- 相手との関係性に応じて語調を選ぶことが大切です。
- ビジネス文書では漢語調を基本とし、プライベートでは和語調が自然です。
このように、6月の書き出しには、天候や風物詩に触れた言葉を選ぶことで、自然な季節感と丁寧な印象を同時に与えることができます。
カジュアルな手紙で使える表現
親しい相手への手紙やハガキでは、かしこまった言い回しよりも、自然でやわらかい口調の時候の挨拶が好まれます。特に6月は梅雨や初夏の風景など、季節感が豊かなので、情景を交えた表現を取り入れるとより印象的になります。
カジュアルな時候の挨拶例
- 紫陽花がきれいに咲く季節になりましたね。
- 雨の日が続いていますが、体調など崩されていませんか?
- 梅雨入りして、しっとりとした毎日が続いています。
- 日差しが強くなり、夏の気配を感じるようになりました。
使用シーンの例
- 友人への近況報告
- お中元を送る前の挨拶文
- 季節の便りとしての手紙
例えば、「梅雨入りして毎日じめじめしていますが、あなたはお元気ですか?」と書けば、日常の空気感とともに、相手を思いやる気持ちが伝わります。
ただし、あまりにもくだけすぎると文面として軽くなりすぎてしまう可能性があるため、文末に「くれぐれも体調には気をつけてね」などの一言を添えるとバランスが取れます。
このように、カジュアルな手紙では形式にとらわれず、相手との関係性に合った表現で気持ちを届けることが大切です。
学校関係の手紙に適した挨拶
学校関係の文書には、保護者宛の案内や連絡帳、PTA活動の書簡などがあり、形式的すぎず、しかし失礼のない挨拶文が求められます。6月は季節の変わり目でもあるため、天候や生活の節目に触れる挨拶が適しています。
適した挨拶の例
- 衣替えの季節を迎え、子どもたちの制服も夏仕様となりました。
- 梅雨の時期に入り、雨の日が続いております。
- 紫陽花が咲き始め、校庭にも季節の移ろいを感じます。
- 気温の変化が大きいこの頃、体調管理が難しい時期です。
具体的な使用例
- 拝啓 梅雨に入り不安定な天候が続いておりますが、保護者の皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
- 拝啓 初夏の風が心地よく感じられる季節となりました。お子様も元気に登校されていることと存じます。
学校文書では、過度に堅苦しい表現を避けつつも、季節に触れた配慮ある言葉が基本です。
また、雨の多い時期は登下校時の注意点や行事の延期などに関する案内も増えるため、「雨の日が続きますが、くれぐれもご自愛くださいませ」といった締めの言葉を加えると好印象です。
このように、学校関連の手紙では、相手の生活リズムやお子様の状況に配慮した挨拶が求められます。
お礼状に使える6月の季節表現
6月のお礼状では、感謝の気持ちを伝えるとともに、季節感のある言葉を添えることで、丁寧で心のこもった印象になります。梅雨や初夏といった自然の描写を取り入れることで、形式的な文書にも温かみが生まれます。
おすすめの季節表現
- 長雨の続く中、心温まるお心遣いをありがとうございました。
- 紫陽花の花が色づく季節、素敵なお品を頂戴し、感激しております。
- 蒸し暑さが感じられるこの時期に、清涼感ある贈り物を頂きありがとうございました。
- 初夏のさわやかな風に心癒される日々、温かなご配慮に深く感謝申し上げます。
お礼状の文例
- 拝啓 梅雨の候、貴殿におかれましてはご健勝のことと拝察いたします。このたびはご丁寧なお心遣いをいただき、心より御礼申し上げます。
注意点として、感謝の言葉と季節の表現のバランスが大切です。どちらかが長くなりすぎると、文章全体が読みにくくなってしまうため、2~3文のなかで自然にまとめると読み手にも好印象です。
お礼状にふさわしい季節感を添えることで、形式だけでなく心のこもった手紙に仕上げることができます。
季節の言葉を活かした結び文
手紙やメールの最後に添える「結び文」には、相手への気遣いや、文全体の印象を整える役割があります。6月においては、梅雨や初夏といった季節の移ろいを表す言葉を取り入れることで、自然で余韻のある締めくくりになります。
例えば、以下のような表現が効果的です。
6月に使いやすい結び文の例
- 長雨が続きますが、どうぞお身体を大切にお過ごしください。
- 梅雨寒の日もございますので、くれぐれもご自愛くださいませ。
- 紫陽花の彩りに心癒される季節、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
- 夏至を迎え、日差しが強くなってまいりました。体調など崩されませんようお祈りいたします。
- 蒸し暑い日が続いております。お元気でお過ごしになられますように。
このような文面は、ビジネスでもプライベートでも活用できます。フォーマルな場面では「ご多幸をお祈り申し上げます」や「ご清栄を心よりお祈りいたします」といった定型表現と組み合わせることで、礼儀正しい印象を与えることができます。
一方で、親しい相手に対しては、「雨の日が続きますが、お互い元気に過ごしましょうね」など、やわらかい語調の表現が適しています。
ただし、実際の気候とあまりにもずれてしまうと違和感を与える場合があります。たとえば、晴天が続く日々に「長雨の折」と書いてしまうと、不自然に感じられることもあるため注意が必要です。
季節の言葉をうまく取り入れた結び文は、読み手の心に残る手紙づくりに欠かせない要素です。天候や時期に応じた表現を心がけることで、温かみのある印象を与えることができます。
総括:6月の時候の挨拶一覧と使い分け例を徹底解説
記事のポイントをまとめます。
- 向暑の候は5月下旬から6月全般に使える
- 初夏の候は6月上旬までの清涼感ある表現に適している
- 青葉若葉の候は春から初夏への移り変わりを伝える表現
- 芒種の候は6月5日頃から田植えの時期に合わせて使用できる
- 薄暑の候は軽い暑さを感じる初夏にぴったりな語句
- 入梅の候は6月11日頃以降の梅雨入りにふさわしい
- 長雨の候は雨が続く6月中旬〜下旬に自然な表現となる
- 夏至の候は6月21日頃以降の暦の節目を意識した挨拶に適している
- 小夏の候は本格的な夏の前触れを柔らかく伝えられる
- ビジネス文では時候の挨拶に「貴社ますますのご清栄を~」を添えると丁寧
- カジュアルな手紙では紫陽花や雨など身近な自然表現が効果的
- 学校文書では衣替えや梅雨入りといった生活の変化に触れると自然
- お礼状には「蒸し暑さの中ご配慮いただき~」などの季節感ある感謝文が向いている
- 書き出しは相手との関係性に応じて漢語調と和語調を使い分けるべき
- 結び文では体調への気遣いや季節感の余韻を添えるのが基本