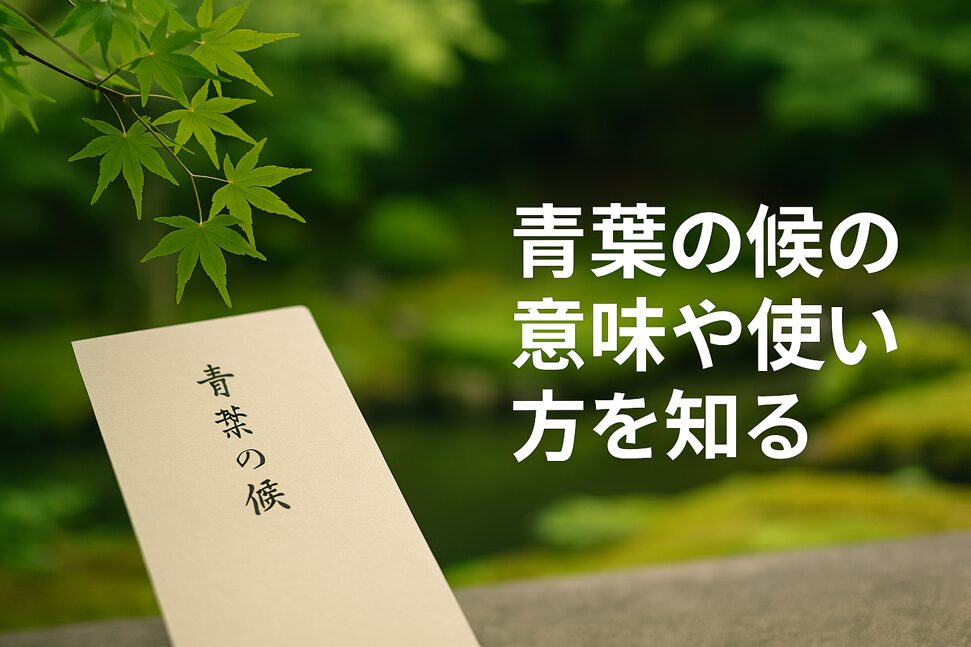季節の移ろいを言葉で伝える日本の手紙文化には、美しい表現が数多く存在します。その中でも「青葉の候」は、春から初夏への変わり目に使われる代表的な時候の挨拶です。木々の葉が青々と茂り始めるこの時期にふさわしいこの言葉は、手紙の書き出しに自然の風景と季節感を添える役割を果たします。
しかし、実際に「青葉の候」を使おうとすると、「いつからいつまで使えるのか」「他の挨拶表現との違いは何か」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「青葉の候」の読み方や語源、使うべき時期、類似表現との違い、そして手紙における活用法までを幅広く解説します。
ビジネス文書や目上の方への手紙、カジュアルなやり取りなど、さまざまなシーンで使える例文もご紹介しますので、季節の挨拶としての「青葉の候」を正しく、そして上手に使いたい方はぜひ参考にしてください。
- 青葉の候の正しい意味と読み方
- 使うべき時期や適切なタイミング
- 類似表現との使い分け方
- 手紙での具体的な使用例や注意点
青葉の候の意味や使い方を知る
・青葉の候の読み方と語源
・青葉の候はいつ使うのが適切か
・若葉の候との違いを解説
・新緑の候と使い分けるポイント
・青葉の候の例文と使用例
青葉の候の読み方と語源
読み方
- 「青葉の候」は あおばのこう と読みます。
意味・使い方
- 手紙やはがきなどの書き出しで使われる時候の挨拶の一つです。
- 「青々とした木々の葉が生い茂る季節になりましたね」という季節の美しさを伝える表現です。
語源の構成
- 「青葉」
- 春から初夏にかけての、青々と茂る木の葉のこと
- 「新緑」よりも色が深く、生命力を感じさせる言葉
- 「候(こう)」
- 古典的な表現で「〜の季節」「〜の頃」という意味
- 「青葉の候」= 青葉の季節になりました という意味合い
文化的背景
- 日本では昔から、自然の移ろいを言葉で伝える手紙文化が大切にされてきました。
- 「青葉の候」もその一例で、相手を気遣う丁寧な挨拶として定着しています。
使用シーンの注意点
カジュアルな文面にはやや堅い印象になることもあります。漢語調でやや改まった印象を与えるため、フォーマルな手紙(ビジネスや目上の人への挨拶状など)に適しています。
🌿フォーマルなビジネス文例
拝啓 青葉の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
(本文続く)
🌱 目上の人や丁寧な私信で使う文例
拝啓 青葉の候、○○様にはますますご健勝のことと存じます。
日頃より何かとお心遣いを賜り、厚く御礼申し上げます。
(本文続く)
🌸 柔らかめな文面・親しい関係向け(少しカジュアル)
青葉の候、風が心地よい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
お変わりなくお元気でいらっしゃることを願っております。
(本文続く)
青葉の候はいつ使うのが適切か
使用時期の目安
- 5月中旬〜6月中旬が一般的
- 特に立夏(5月5日頃)〜梅雨入り前がベストタイミング
季節感との関係
- 春の新芽が成長し、木々が青々と茂る季節にマッチ
- 暦の上では夏でも、爽やかな気候と若葉の美しさが感じられる時期
地域差に注意
- 沖縄・九州など早く梅雨入りする地域では、6月初旬以降は「梅雨の候」などが自然
- 本州エリアでは6月10日前後まで使っても違和感なし
配慮のポイント
単にカレンダーを見るのではなく、
➤ 相手の住んでいる地域の季節感を想像して使うと丁寧な印象に
若葉の候との違いを解説
読み方と意味
| 表現 | 読み方 | 意味・イメージ |
|---|---|---|
| 若葉の候 | わかばのこう | 芽吹いたばかりの柔らかく明るい緑の葉が出始める頃 |
| 青葉の候 | あおばのこう | 若葉が育ち、濃く力強い緑の葉が茂る頃 |
使用時期の違い
| 表現 | 適した時期 | 季節の位置付け |
|---|---|---|
| 若葉の候 | 4月下旬〜5月上旬 | 春の終わり〜初夏の入り口 |
| 青葉の候 | 5月中旬〜6月中旬 | 初夏の始まり〜梅雨前 |
ニュアンスの違い
| 若葉の候 | 青葉の候 |
|---|---|
| 明るくやわらかく、みずみずしい印象 | 濃く深い緑で、力強さ・生命力のある印象 |
| 春らしい軽やかさ | 初夏の落ち着いた深み |
使い分けのポイント
- 「若葉の候」は、芽吹き始めたばかりの季節にふさわしい言葉。
- 「青葉の候」は、すでに青々と葉が茂っている季節にぴったり。
- 時期を間違えると、季節感にズレが出るため注意。
✅ 例えば:5月下旬に「若葉の候」と書くと、
すでに青葉の時期なので「少し遅れている印象」を与えてしまうかも。
フォーマルな手紙では特に重要
季節の移ろいに敏感な日本文化では、細かな使い分けが信頼や好印象につながることもあります。
ビジネス文書や礼状などでは、時候の表現の正確さが相手への配慮になります。
新緑の候と使い分けるポイント
使用時期の違い
| 表現 | 適した時期 | 季節感 |
|---|---|---|
| 新緑の候 | 4月下旬〜5月中旬 | 春の終わりの軽やかさ・若々しさ |
| 青葉の候 | 5月中旬〜6月中旬 | 初夏の力強さ・成熟した自然の豊かさ |
ニュアンスの違い
| 新緑の候 | 青葉の候 |
|---|---|
| 明るく清らか、軽やかな印象 | 濃く力強い、生命感あふれる印象 |
| 春らしいみずみずしさ | 初夏らしい落ち着きと豊かさ |
使い分けのポイント
- 🌸 春の終わり〜GW前後なら → 新緑の候
- 🌿 初夏・5月中旬以降〜梅雨前なら → 青葉の候
例:
✔ 5月5日 → 新緑の候(まだ軽やか)
✔ 5月20日 → 青葉の候(緑が深くなってきた)
まとめ
| 比較ポイント | 新緑の候 | 青葉の候 |
|---|---|---|
| 葉の状態 | 若くて淡い緑 | 成長し濃い緑に |
| 季節の印象 | 春の終わりの爽やかさ | 初夏の成熟と豊かさ |
| 使用時期 | 4月下旬〜5月中旬 | 5月中旬〜6月中旬 |
| 手紙の印象 | 軽やか・爽やか | 落ち着き・力強さ |
どちらも美しい日本語の表現ですが、「季節に合った言葉選び」をすることで、手紙の品位や丁寧さがグッと上がります✨
青葉の候の例文と使用例
基本情報
- 読み方:あおばのこう
- 使用時期:5月中旬〜6月中旬
- 意味:青々と茂る木々の葉に季節の移ろいを感じさせる挨拶
① フォーマル・ビジネスでの使用
📝 例文(丁寧な書き出し)
拝啓 青葉の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
🔎 ポイント
- ビジネス文書・取引先への挨拶に適した表現
- かしこまりつつも季節感を伝える
② 目上の人・あらたまった私信で
📝 例文(礼儀正しい文面)
拝啓 青葉の候、○○様にはますますご健勝のことと存じます。
日頃より何かとご配慮を賜り、心より御礼申し上げます。
🔎 ポイント
- 先生・上司・親族など目上の相手への丁寧な手紙に
- 続きに感謝・報告・近況などを添えると自然
③ カジュアルな私信や近況報告に
📝 例文(やや柔らかめ)
青葉の候、さわやかな風が心地よく感じられる季節となりました。
お変わりなくお元気にされていますか?
🔎 ポイント
- 親しい人や友人への手紙・メールに向いた文面
- 季節の風や空気感を添えるとより自然な印象に
④ 結びの挨拶に季節感を出す場合(補足)
これからますます緑が深まってまいります。どうぞご自愛のうえ、お過ごしください。
⚠️ ※「青葉の候」を文頭に使った場合は、結びで繰り返さないように注意しましょう。違う季節の言い回しや自然の描写で変化をつけると◎
🎯 使い方のまとめ
| シーン | 書き方の特徴 | 使用ポイント |
|---|---|---|
| ビジネス | かしこまった言い回し | 「拝啓~ご清栄のことと~」 |
| 目上の方 | 丁寧な敬語 | 健勝・ご多幸など体調への配慮を含める |
| カジュアル | 柔らかい表現 | 季節の話題+問いかけで親しみを出す |
青葉の候を上手に手紙に使う
・ビジネス文書での青葉の候の例文
・目上の方へ送る際の注意点
・カジュアルな手紙に使うコツ
・立春の候からの移り変わり
・早春の候・向春の候との違い
・余寒の候・厳寒の候との関連性
ビジネス文書での青葉の候の例文
一般的な挨拶文(取引先などへの定型文)
拝啓 青葉の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
(本文)
梅雨入りも間近となってまいりましたが、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
敬具
お礼状に使う場合
拝啓 青葉の候、貴社におかれましてはますますご清栄のことと存じます。
先日はご多忙の折にもかかわらず、温かいご対応を賜り誠にありがとうございました。
(本文)
初夏の折、皆様のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。
敬具
お詫び・フォローアップに使う場合
拝啓 青葉の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたびは弊社の不手際によりご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
(本文)
新緑の美しい季節、どうぞご自愛のうえお過ごしくださいませ。
敬具
招待・案内文に使う場合
拝啓 青葉の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたび、弊社では下記の通り展示会を開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。
(本文)
初夏のみぎり、皆様にお目にかかれますことを楽しみにしております。
敬具
✨ ワンポイントアドバイス
結びでは、「梅雨の足音〜」「初夏のみぎり〜」「ご自愛ください」など、重複を避けた季節感のある表現を添えるとスマートです。
目上の方へ送る際の注意点
1. 頭語(拝啓・謹啓)を忘れずに使う
- 拝啓:一般的な丁寧表現
- 謹啓:より丁重で格式の高い表現(正式な場面で使用)
✏️ 例:「拝啓 青葉の候、○○様には…」
2. 時候の挨拶の後に、相手をたたえる言葉を添える
- 相手の健康・活躍・繁栄を祝う一文を加えることで、より丁寧に
✏️ 例:「青葉の候、○○様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
3. 同じ季節表現の繰り返しを避ける
- 文頭で「青葉の候」と使ったら、結びでは異なる自然表現にする
❌ 結びにも「青葉が〜」を使うと冗長に
✅ 「梅雨入りも近づいておりますが〜」「爽やかな季節となりましたが〜」などを用いる
4. 結語(敬具・謹言)で締める
- 頭語とセットで結語をきちんと記載することが重要
| 頭語 | 対応する結語 |
|---|---|
| 拝啓 | 敬具 |
| 謹啓 | 謹言 |
5. 自然な流れ・配慮を忘れずに
- 形式に偏りすぎず、相手に伝えたい思いや目的が明確になるように
- 季節の表現と本題をなめらかに繋ぐ工夫も大切
📝 目上の方への例文(テンプレート)
拝啓 青葉の候、○○様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、このたびは……(本文)
梅雨入りも近づいてまいりましたが、くれぐれもご自愛のうえお過ごしくださいますようお祈り申し上げます。
敬具
カジュアルな手紙に使うコツ
1. 堅苦しい形式をやわらげる
- 頭語(拝啓など)・結語(敬具など)を省略してOK
- 会話のように、話しかける文体で始めると自然です
✏️ 例:
「青葉の候、気持ちのいい季節になりましたね。」
「青葉の季節、いかがお過ごしですか?」
2. 文体は「です・ます」調でやさしく
- 丁寧すぎず、フレンドリーな雰囲気を意識しましょう
- 「お元気ですか?」「最近どうしてますか?」なども添えると親近感UP
✏️ 例:
「青葉の候、さわやかな風に初夏を感じる今日このごろです。お元気ですか?」
3. 会話調の自然な語りに取り入れる
- 「季節のあいさつ」としてでなく、季節の話題として溶け込ませるのも◎
✏️ 例:
「最近は青葉がきれいで、散歩がとても気持ちいい季節になりましたね。」
4. 違和感があるときは“口語表現”に言い換える
- 「青葉の候」がやや堅く感じるときは、意味を崩さずに言い換えるのもおすすめ
🔁 言い換え例:
・「青々とした木々が美しい季節ですね」
・「新緑が深まってきましたね」
・「緑が濃くなってきて、初夏らしくなってきました」
5. 親しみを込めた近況や季節の話題を入れる
- 季節の話題と、相手の様子を気づかう一文を添えるとやさしい印象に
✏️ 例:
「青葉の候、日差しもずいぶん強くなってきましたね。お変わりありませんか?」
✉️ カジュアルな例文
青葉の候、さわやかな風が気持ちのいい季節になりましたね。
体調を崩しやすい時期ですが、元気にされていますか?
また近いうちに会えるのを楽しみにしています!
カジュアル文面では、“無理に季語を入れる”よりも、“自然に季節感をにじませる”のがコツです。
立春の候からの移り変わり
🌱 1. 立春の候(2月上旬〜中旬)
- 暦の上での「春の始まり」
- 実際はまだ寒いが、春の兆しを感じ始める時期
- ❄️ → 🌤 へと季節が切り替わる瞬間
例文:
拝啓 立春の候、寒さの中にも春の足音が感じられるようになりました。
🌼 2. 早春の候/春寒の候(2月中旬〜3月初旬)
- 春は始まったが、寒さが残っている
- 梅や早咲きの花がちらほら咲き始める時期
☀️ 3. 春暖の候/陽春の候(3月中旬〜4月上旬)
- 春らしい暖かさが広がる
- 桜の便りが聞こえ始める、華やかでうららかな時期
🌿 4. 新緑の候/若葉の候(4月下旬〜5月上旬)
- 芽吹いたばかりの葉が目に鮮やかな季節
- 若くやわらかい緑が風にそよぐ爽やかな春の終わり
🍃 5. 青葉の候(5月中旬〜6月中旬)
- 木々の葉がしっかり成長し、生命力あふれる深い緑に
- 初夏の始まりを告げる、成熟した自然の美しさを表す
例文:
拝啓 青葉の候、緑がいっそう深まる季節となりました。いかがお過ごしでしょうか。
ポイント:移り変わりの美しさを感じるには
- 立春の候 → 希望や兆しを感じる言葉
- 青葉の候 → 成熟や活力を感じる言葉
- どちらも単なる「季節」ではなく、自然の状態や心の変化を繊細に表す日本語独自の文化表現です
実用面での注意
- 相手と「同じ季節を感じている」ことが、丁寧な配慮になります
- 季節感が合っているかどうかを常に意識
- 特に手紙や挨拶文では、使う時期がずれると違和感になることも
早春の候・向春の候との違い
| 項目 | 早春の候(そうしゅんのこう) | 向春の候(こうしゅんのこう) |
|---|---|---|
| 📅 使用時期 | 2月上旬〜3月中旬(立春以降) | 1月下旬〜2月上旬(立春前) |
| 🌡 季節感 | 春の始まりを実感する時期 | 春が近づく気配を感じる時期 |
| 🌱 自然の様子 | 芽吹きの気配、日差しが少し暖かい | 厳しい寒さの中にかすかな春の兆し |
| 💬 ニュアンス | 春を迎えた明るさ・希望 | 春を待ち望む控えめな気持ち |
| 🎯 適した印象 | ポジティブで華やか、動き出す印象 | 上品でしっとり、静かな期待感 |
使用例(文頭)
▸ 向春の候
向春の候、いかがお過ごしでしょうか。まだまだ寒さが続きますが、お元気でお過ごしのことと存じます。
▸ 早春の候
早春の候、春の兆しが感じられる今日このごろ、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。
使い分けのポイント
- 「向春の候」は、まだ冬だが春への期待感を控えめに伝えたいときに
- 「早春の候」は、暦の上で春に入り、春らしさを感じられる頃にぴったり
🌟 例:
- 1月末 → 向春の候(まだ春になっていない)
- 2月10日 → 早春の候(立春を過ぎている)
- 3月初旬 → 早春の候(地域によっては春めいてくる)
余寒の候・厳寒の候との関連性
| 項目 | 厳寒の候(げんかんのこう) | 余寒の候(よかんのこう) |
|---|---|---|
| 📅 使用時期 | 1月上旬〜2月初旬(立春前) | 2月上旬〜2月下旬(立春後) |
| 🌡 季節の状態 | 真冬・最も寒さが厳しい時期 | 暦の上では春、寒さが残っている時期 |
| 💬 ニュアンス | 「寒さのピークですね」 → 冬の厳しさを強調 | 「春なのにまだ寒いですね」 → 残る寒さに対する気遣い |
| 🌸 季節の立ち位置 | 冬の中心・本格的な冬 | 冬の終わり・春の入り口 |
| ☕ 印象 | 寒さへの耐え忍び・静けさ | 春を待つ心・繊細な移ろい |
共通点
- どちらも寒さに関する表現
- 相手の体調や健康を気遣う意図が込められている
- フォーマルな手紙・挨拶文でよく使われる
例文比較
・ 厳寒の候(1月)
拝啓 厳寒の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
寒さも一段と厳しくなってまいりましたが、どうかご自愛くださいませ。
・余寒の候(2月)
拝啓 余寒の候、寒さの中にも少しずつ春の気配が感じられるようになりました。
季節の変わり目でございますので、どうぞお体を大切にお過ごしください。
使い分けのポイント
| シーン | 選ぶべき表現 |
|---|---|
| 1月上旬〜2月3日頃(立春前) | 厳寒の候 |
| 2月4日以降〜2月下旬(立春後) | 余寒の候 |
| 春の気配を少し含めたい時 | 余寒の候 が適切 |
✨ まとめ
- 「厳寒の候」= 冬の真っただ中を描写する言葉
- 「余寒の候」= 春のはじまりに残る寒さを表す言葉
▶ 両者は、冬から春へと季節が移ろう中で自然につながる表現です。
▶ 適切に使い分けることで、手紙に季節感と気配りの心を込めることができます。
青葉の候に関する基本知識と使い方のまとめ
記事のポイントをまとめます。
- 「青葉の候」の読み方は「あおばのこう」
- 青々とした木々の葉が茂る季節を表す言葉
- 「候」は「季節」や「頃」を意味する古典的な語
- 使用時期は5月中旬から6月中旬が目安
- 初夏の自然の生命力を感じさせる表現
- 地域によっては梅雨入りを考慮して使い分けが必要
- 「若葉の候」は4月下旬~5月上旬に使う
- 若葉は淡い緑、青葉は濃く力強い緑を指す
- 「新緑の候」は5月上旬までに使うのが自然
- 季節の成熟度によって時候の挨拶を使い分ける
- ビジネス文書では「拝啓」などの頭語と組み合わせる
- 目上の相手には敬語や丁寧な表現を添えることが大切
- カジュアルな手紙では柔らかい文体に調整する
- 「立春の候」から「青葉の候」までの移ろいを意識すると季節感が出る
- 時候の挨拶は文頭と結びで同じ表現を繰り返さないよう注意が必要
- 寒中見舞いの返事の例文と送る際の注意点まとめ
- 寒い中お越しいただき メールの例文と注意点を詳しく解説
- 1月の時候の挨拶例文集|ビジネスとカジュアルな使い方
- 2月の時候の挨拶 例文と季節感を活かした効果的な表現
- 3月の時候の挨拶 例文|手紙やメールで使える書き方と例文集
- 【4月の時候の挨拶】やわらかい表現を場面別に紹介
- 春の俳句の魅力とは?初心者向けの作り方と例を紹介
- 2月の季語を一覧で紹介!俳句や手紙で使える言葉
- 3月季語一覧|春の訪れを感じる美しい言葉集
- 4月の季語一覧|春の風物や植物を詠む言葉を詳しく解説
- 寒暖の差が激しい時期の挨拶文の書き方と使える例文集
- 「春暖の候」はいつ使う?意味や時期とビジネス例文を解説